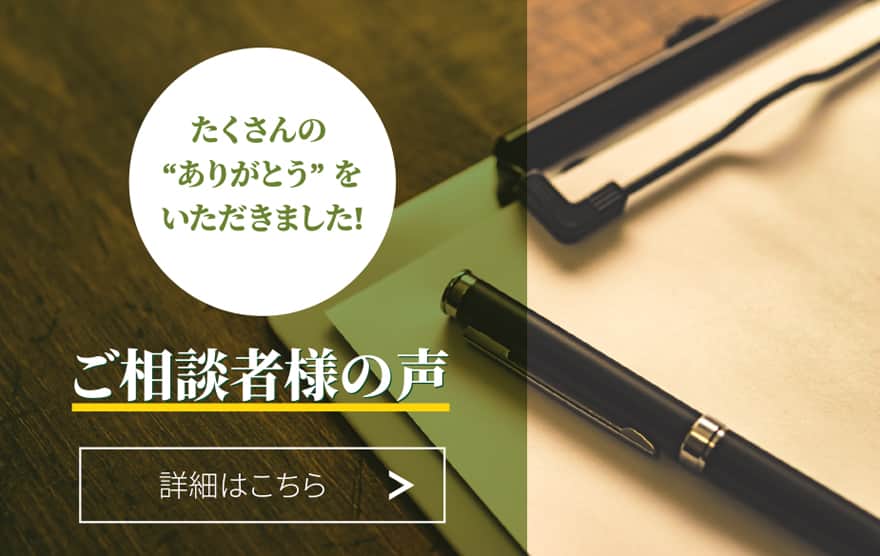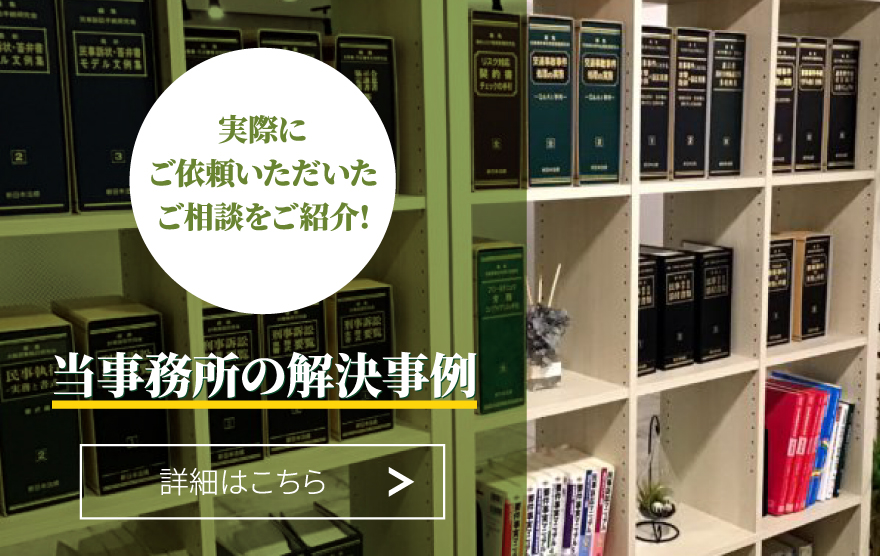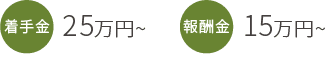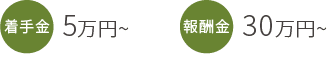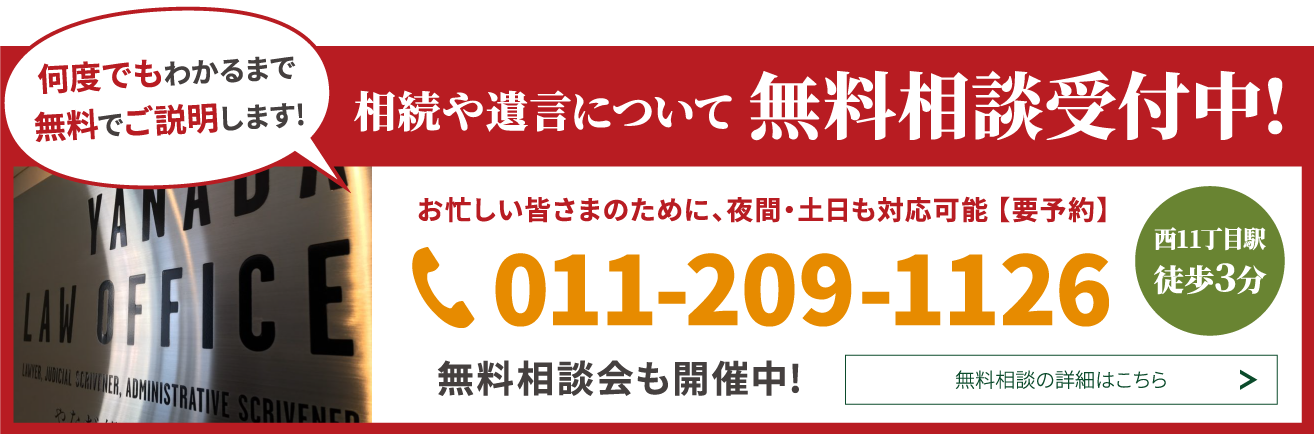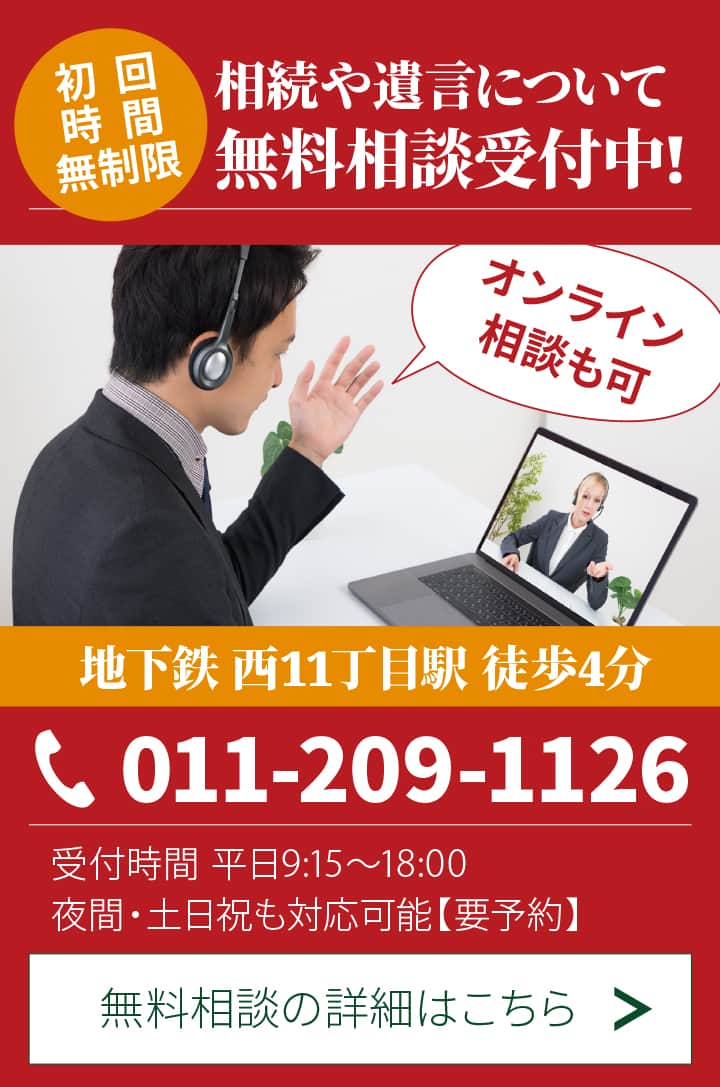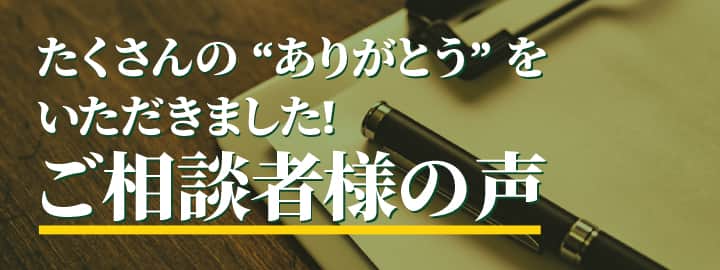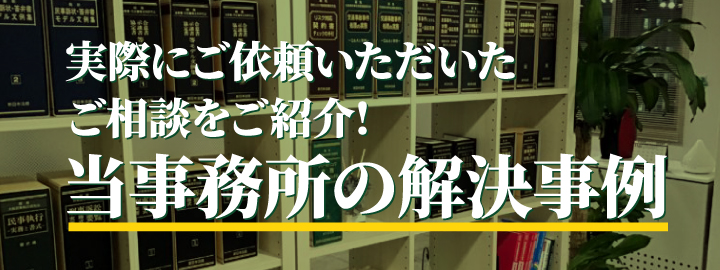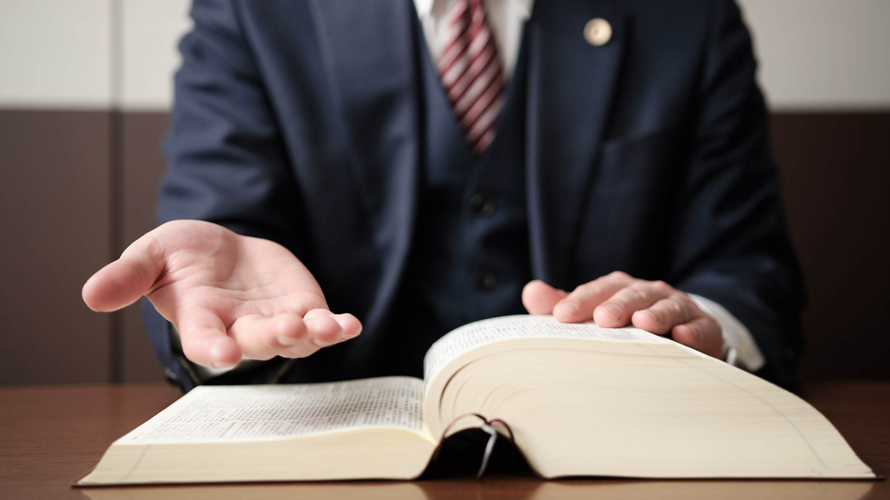
遺言は、故人の最終意思を表示する重要なツールではありますが、実際にその意思を実現するためには、様々な手続きが必要となります。例えば、自宅を献身的に介護してくれた義理の娘に遺贈する旨の遺言が残されていたとしても、実際に、その義理の娘が自宅を譲り受けるためには、自宅の名義変更等の手続きが必要になります。
遺言執行者が指定されていない場合には、遺贈による不動産の名義変更は、遺贈によって不動産を譲り受けた受遺者と相続人が共同して申請することになりますが、遺贈に反対する相続人がいる場合には、トラブルとなったり、手続き自体がストップしてしまうおそれがあります。
今回のコラムでは、遺贈に反対する相続人がいるケースを例に、遺言執行者選任の申し立てについて解説したいと思います。
そもそも遺言執行者とは
遺言執行者とは、簡単に言うと、遺言を書いた本人の代わりに遺言の内容を実現させる人を指します。遺言が実際に執行される時点では、遺言を書いた本人は亡くなっていますから、遺言の内容を自らの手で実現させることはできません。そのため、遺言執行者が遺言を書いた本人に代わって遺産の分配や相続に関する手続きを行います。
遺言によって遺言執行者を指定することが可能ですが、遺言の内容として遺言執行者を指定するか否かは、遺言者の自由意思に委ねられています。遺言執行者を指定しなかったとしても、そのことにより遺言自体の効力に影響はありません。遺言執行者がいない場合には、原則として、相続人が様々な手続きを行うことになります。
不動産の遺贈とその名義変更
不動産が遺贈された場合、確定的に不動産の所有権を取得するためには、しっかりとその名義を変更する必要があります。また、2024年の改正法施行により、遺贈によって不動産を譲り受けた場合に、その名義変更を申請することは義務となっています。
例えば、冒頭で挙げた例のように、義理の父から不動産の遺贈を受けた義理の娘は、譲り受けた不動産の名義変更(遺贈による所有権移転登記)を申請する必要があります。
遺贈による所有権移転登記の申請は、遺言執行者がいる場合には、受遺者と遺言執行者が共同して、遺言執行者がいない場合には、受遺者と相続人が共同して行います。
遺言執行者が指定されていない場合でも、受遺者と相続人の関係が良好であれば、特段問題はないのですが、受遺者と相続人が不仲であったり、遺贈に反対する相続人がいるケースでは、名義変更の際にトラブルになるケースも少なくありません。
遺言執行者選任の申し立て
遺言執行者は、遺言によって指定することができますが、実は、遺言者本人が亡くなった後でも、家庭裁判所に申し立てを行うことによって、選任することが可能です。
民法第1010条
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
遺言によって遺贈を受けた受遺者は民法第1010条で言う「利害関係人」にあたりますので、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言執行者が選任されると、以後は、遺言執行者と受遺者のみで不動産の名義変更手続きを進めることができますので、「不仲な相続人」、「遺贈に反対している相続人」、「疎遠な相続人」等との一切のやり取りが不要となり、手続きを円滑に進めることが可能となります。なお、遺言執行者として専門の弁護士を選任することも可能です。
おわりに
今回のコラムでは、遺贈に反対する相続人がいるケースを例に、遺言執行者選任の申し立てについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
遺言内容の実現に非協力的な相続人がいる場合でも、相続人は遺言内容の実現に協力する義務が本来ありますので、最終的には調停や審判で協力を取り付けることも可能です。
ただ、純粋に遺言内容の実現のためだけに、調停や審判を行うのは手間がかかりますし、かえって相続人との関係を悪化させる事態にもなりかねません。遺言執行者選任の申し立てという手段であれば、相続人を関与させずに手続きを進めることができますので、ケースバイケースの部分もありますが、穏当でスマートな解決になる場合があります。
「弁護士に相談する」というと、何か争いを大きくするイメージを持たれる方も少なからずいらっしゃいますが、実は、法律のプロだからこそできる穏便な解決方法も存在します。相続でお困り事がある場合には、争いが大きくなる前に専門の弁護士に相談することが大切となります。
当事務所は、相続に精通した弁護士が、皆様の相続問題の解決に尽力いたします。初回無料にて相談を行っておりますので、相続・遺産分割・不動産相続など、相続に関することでお悩みのある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。相続人調査や相続財産調査にも対応しております。