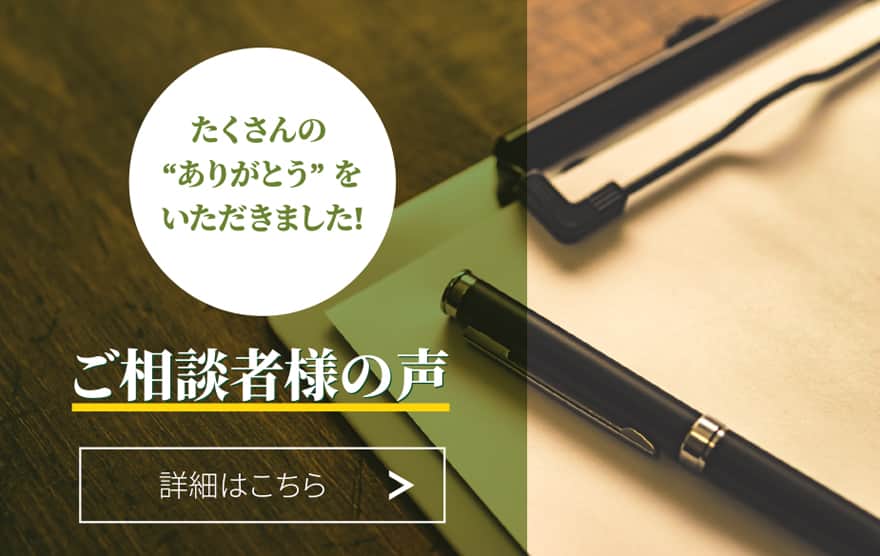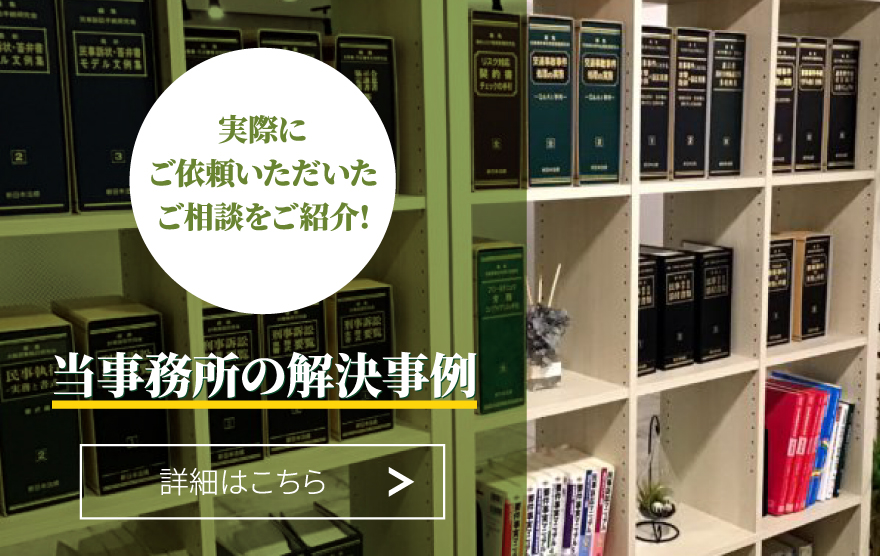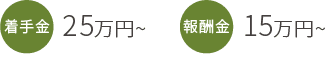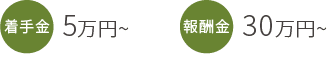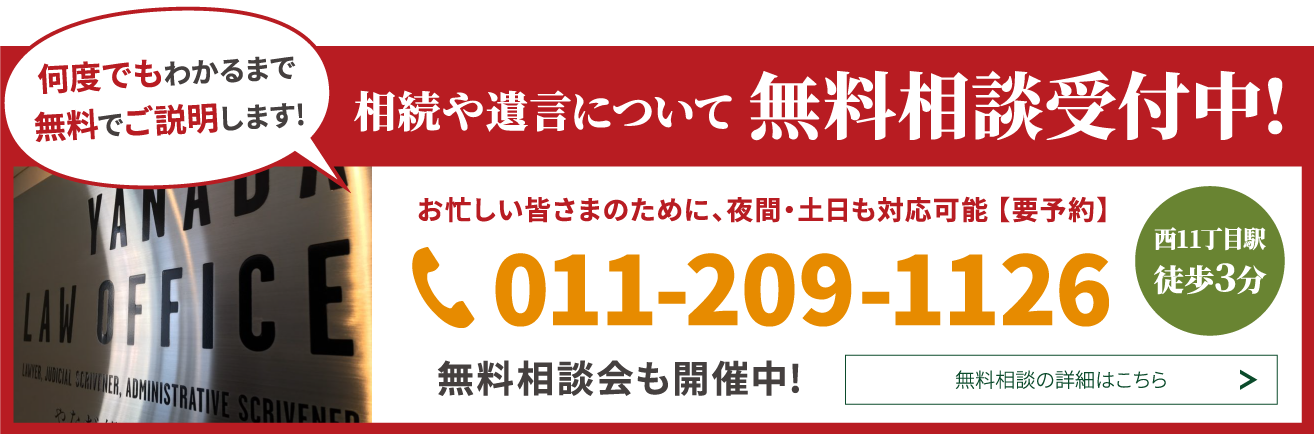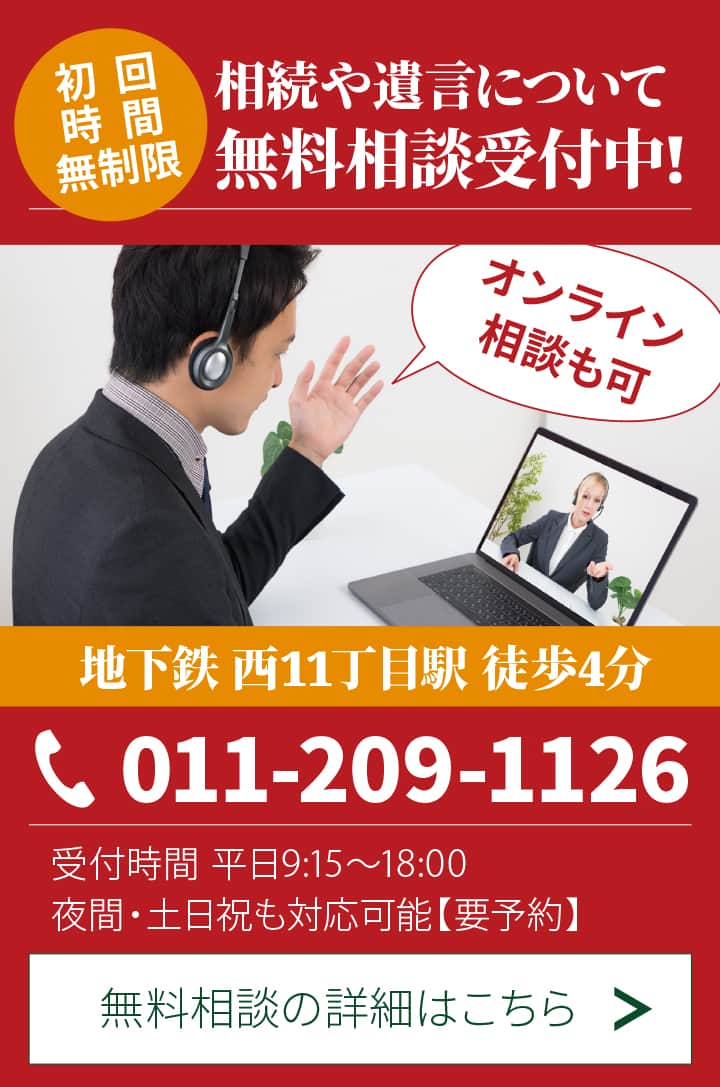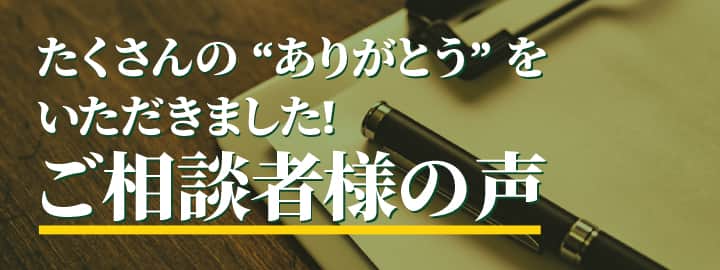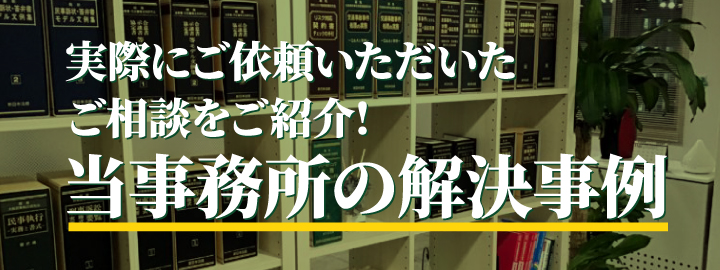家族が亡くなったとき、残された人々が直面する大きな課題のひとつが「相続」です。相続と聞くと「財産をどう分けるか」というイメージが強いですが、その前提として必ず確認しなければならないのが「誰が相続人になるのか」という問題です。実際の相談でも、「配偶者と子どもがいる場合はどう分けるのか」「兄弟姉妹にも権利があるのか」といった質問は非常に多く寄せられます。
この「誰が相続人になるか」を定めているのが、民法における「相続の順位」という仕組みです。順位を理解していないと、相続人に含まれない人と協議をしてしまったり、本来相続人となるべき人を除外したまま協議を進めてしまう等、余計なトラブルの火種になりかねません。
そこで、今回のコラムでは、相続の順位について基本からわかりやすく解説したいと思います。
相続の順位とは何か
「相続の順位」とは、被相続人(亡くなった人)の財産を、誰がどの順番で相続できるのかを定めた法律上のルールのことです。相続が開始したときには、自動的にこの順位に従って相続人が決まります。
ここで最初に押さえておきたいのは、配偶者は常に相続人になるという点です。結婚している夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者は必ず相続人となります。そのうえで、血縁関係にある人々が「第1順位」「第2順位」「第3順位」という形で定められています。
つまり、相続順位を理解するうえで必要なのは、「配偶者がいるかどうか」と「血縁者のどの順位が該当するのか」を確認することなのです。
具体的な相続の順位
子どもが最優先(第1順位)
最も優先的に相続権を持つのは、子どもです。子どもが存命であれば、配偶者と一緒に相続人となります。
ここで重要なのが「代襲相続」という仕組みです。仮に子どもがすでに亡くなっている場合、その子、つまり孫が代わりに相続人となります。さらに孫が亡くなっている場合はひ孫へと続きます。このように、直系卑属の相続権は世代を下って引き継がれていくのです。
なお、養子縁組をした養子も、実子と同じ立場で相続権を持ちます。
■第1順位:子ども(直系卑属)
■子が死亡している場合 → 孫が代襲相続
子どもがいないときは親へ(第2順位)
子どもがいない場合に相続権を持つのは、父母などの直系尊属です。被相続人の親が存命であれば親が相続します。親がすでに亡くなっている場合は、祖父母に相続権が移ります。
ただし、この順位は「子どもがいない場合に限る」というのがポイントです。子どもが一人でもいれば、親は相続人にはなれません。
■第2順位:父母などの直系尊属
■親が死亡している場合 → 祖父母
親もいなければ兄弟姉妹(第3順位)
子どもも親もいない場合、相続権を持つのは兄弟姉妹です。さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子ども、すなわち甥や姪が代襲相続します。ただし、甥姪の子どもにまでは相続権が及びません。
以前は兄弟姉妹が相続人となるケースは比較的少ない傾向にありましたが、未婚率の上昇に伴い、今後、兄弟姉妹や甥・姪が相続になるというケースは増えることが予想されます。
■第3順位:兄弟姉妹
■亡くなっている場合 → 甥姪が代襲(ただし一代限り)
配偶者と他の相続人の関係
配偶者は常に相続人となりますが、具体的にどの順位の血縁者と組み合わせになるのかが実務上重要です。
たとえば、配偶者と子どもがいる場合は、配偶者と子どもが共同で相続人となります。配偶者と親がいる場合も同様に両者が相続人となります。兄弟姉妹の場合も同じです。そして、血縁者が誰もいなければ、配偶者が単独で財産を相続します。
このように「配偶者+順位」という組み合わせで、実際の相続人が確定します。
■ 配偶者+子ども → 第1順位
■ 配偶者+親 → 第2順位
■ 配偶者+兄弟姉妹 → 第3順位
■ 配偶者のみ → 他に相続人がいない場合
相続の順位をめぐる典型的な誤解
相続の順位は一見シンプルですが、実際の相談現場では多くの誤解が見られます。
代表的なのは、内縁関係の配偶者に関するものです。事実婚として長年一緒に暮らしていたとしても、法律上の婚姻届を出していなければ相続権はありません。財産を残したい場合には、遺言書を作成しておく必要があります。
また、再婚相手の連れ子も、養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。実際に「再婚した夫の連れ子に財産を残したい」という相談は多くありますが、この場合も遺言や養子縁組といった法的な手続きが必要です。
さらに、兄弟姉妹が亡くなっていて、その甥や姪が相続人になるケースも誤解されやすい部分です。「甥姪の子どもまで相続できるのではないか」と思われがちですが、代襲相続が認められるのは一代限りであり、甥姪の子には相続権はありません。
■内縁の配偶者には相続権がない
■義理の子は養子縁組をしない限り相続権がない
■甥姪が相続できるのは代襲相続の一代限り
相続順位の知識が役立つ場面
相続順位を理解しておくことは、実務上きわめて重要です。
たとえば、遺産分割協議を行うときには「誰が相続人か」を確定しなければ協議自体が無効になることがあります。相続放棄があった場合にも、その次の順位に相続権が移るため、順位の理解は欠かせません。
また、遺言書を作成する際にも、想定される相続人を正しく把握しておく必要があります。誤解したまま遺言を残してしまうと、相続人の範囲と齟齬が生じ、かえって争いの原因となることもあるのです。
役立つ場面の例
■遺産分割協議の当事者を確定する
■相続放棄があったときに次順位に移る流れを理解する
■遺言書を作る際に想定される相続人を確認する
こうした知識を持っているだけでも、相続にまつわる不安を大きく減らすことができます。
おわりに
相続の順位は、法律で厳格に定められた仕組みです。基本を押さえてしまえば、非常にシンプルです。
■配偶者は常に相続人になる
■第1順位は子ども(代襲は孫、ひ孫へと続く)
■子どもがいなければ親(祖父母)
■親もいなければ兄弟姉妹(代襲は甥姪まで、一代限り)
このルールを理解しておけば、「誰が相続人になるのか」で迷うことはありません。相続の実務においては、まず順位を確認することが、トラブルを防ぐ第一歩となります。
もし「自分のケースではどうなるのか」「相続放棄があった場合に次は誰が相続人になるのか」といった疑問がある方は、早めに専門家に相談することをおすすめします。誤った対策や手続きを行うとかえって争いの火種となってしまうおそれがあるので、相続専門の弁護士に相談することが家族にとってもっとも安心な相続につながります。
当事務所は、相続に精通した弁護士が、皆様の相続問題の解決に尽力いたします。初回無料にて相談を行っておりますので、相続・遺産分割・不動産相続など、相続に関することでお悩みのある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。相続人調査や相続財産調査にも対応しております。