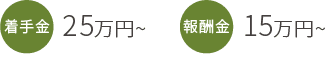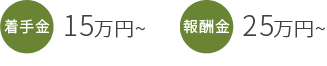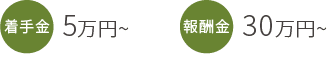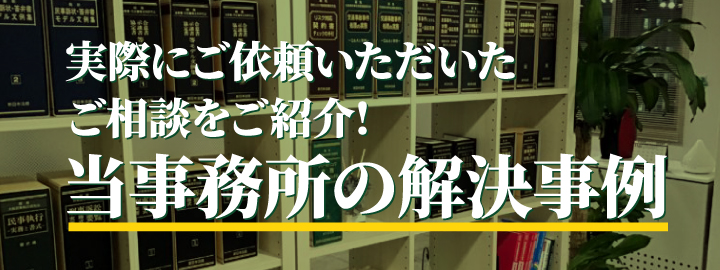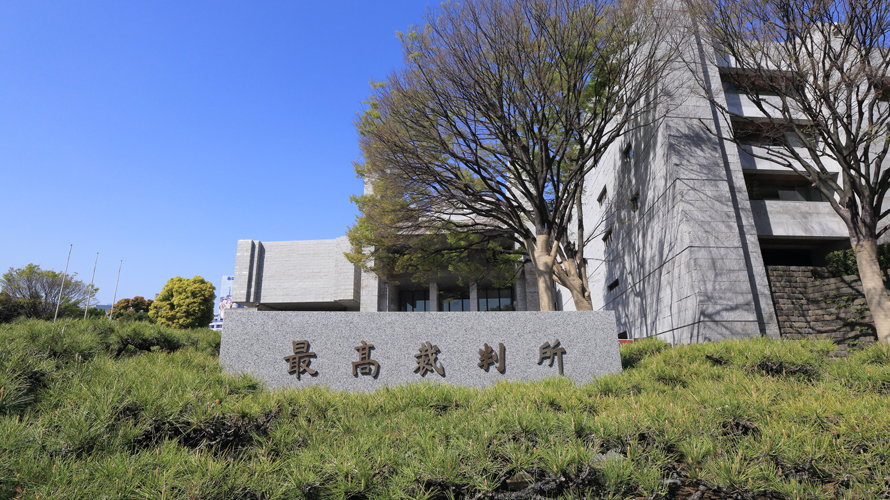
不動産の相続税を算定する際の評価基準について争う注目の裁判。今週、3月15日に最高裁で弁論が開かれ、来月、4月19日に判決が下される予定です。現在広く利用されている不動産購入による相続税対策に影響を及ぼすため、注目が集まっています。今回のコラムでは、裁判で争われている点や、不動産購入による相続税対策にどのように影響がでるのか、解説したいと思います。
相続税対策としての不動産購入
現状、不動産を購入すると、相続税を節約することができます。
日本では相続税を資産の評価額に応じて課していますが、資産を様々なものに換えることによって評価額を落とし、相続税の額を減らすことが可能です。また、課税される額が変わると、相続税の税率も変わるため、その分も節約することができます。
特に不動産は、その価値を算定する基準として、国税庁が発表している「路線価」というものをベースに算定されるのが一般的ですが、その「路線価」による評価額は、実際に取引される価格である実勢価格とは大きな差があるため、その差額分にかかる相続税を節約することができますし、評価額が下がれば税率も下がります。
また、不動産を購入する際に、借入をすることによって、それを負債として計上し、更に相続財産を圧縮するという手法も広く知られています。
相続税対策としての不動産購入のポイント
■路線価と実勢価格との差を利用して評価額を下げる
■評価額が下がれば税率も下がるので合わせて大きな節税効果が見込める
■不動産購入の際の借入を負債として計上し、相続財産を圧縮できる
相続税対策としての不動産購入について詳しくは
「第32回相続コラム 相続対策と不動産の購入について」をご覧ください。
路線価を算定基準とすることの是非についての争い
不動産の相続税は、一般的に「路線価」を基準に評価額が算定される旨が国税庁の「財産評価基本通達」によって示されています。ただし、同通達では、路線価に基き評価した結果と実勢価格との差が大きく、そのまま路線価で評価することが「著しく不適当」な場合には、独自に再評価できるとの例外規定も設けています。
今回の裁判では、上記の例外の適用の是非が問われており、原告側は、不動産を「路線価」に基き算定したのに対し、国税当局は、今回のケースで路線価で評価するのは「著しく不適当」として、独自に鑑定評価し、追徴課税したという事案です。
今回のケースでは、原告側の節税対策により、13億円以上の不動産及びその他の財産を相続しているにも関わらず、路線価に基き不動産の価格を評価し、さらに負債を計上することによって、結果、支払う相続税が「0円」となっているため、国税当局が、それを「著しく不適当」として、「路線価」による算定を否定し、独自に鑑定評価し追徴するのも、うなずけます。実際に、一審、二審では、国税当局の主張を認めています。
最高裁の判断で注目される点
国税当局の主張がもっともだとしても、「著しく不適当」とは、どのような場合を指すのか、なんらかの基準が必要なように思えます。
法律の適用については、事案解決のための具体的妥当性は志向されるべきですが、他方で、法律=ルールは、一般市民の判断・行動の指針となるため、自身の行動の結果が予測可能なように、明確であるべきという要請もあります。
どのような場合が「著しく不適当」といえるのか、その判断基準が不明瞭なまま適用されると、恣意的な賦課徴収がなされる危険性があり、例外的な適用を受ける側からすると不平等な法適用にもなりかねません。また、例外的な法適用をおそれ、経済活動が萎縮してしまうおそれもあります。
最高裁の判断で、どのような場合に「著しく不適当」として、「路線価」によらない不動産価格の評価を認めるのか注目したいところです。