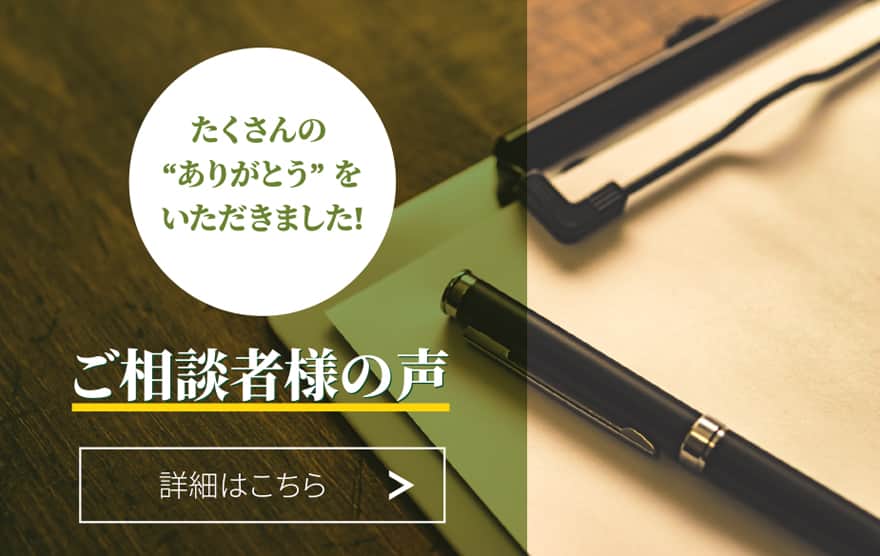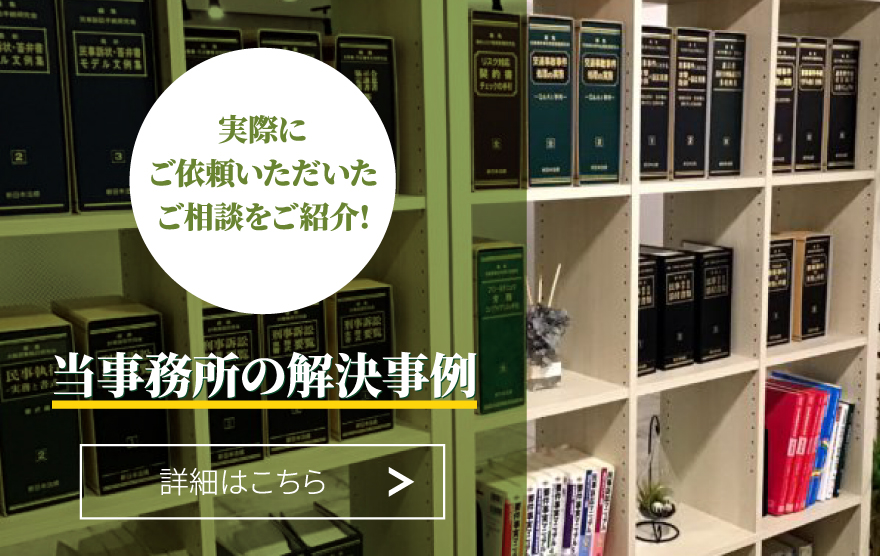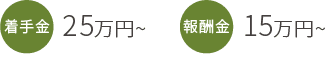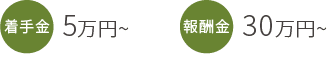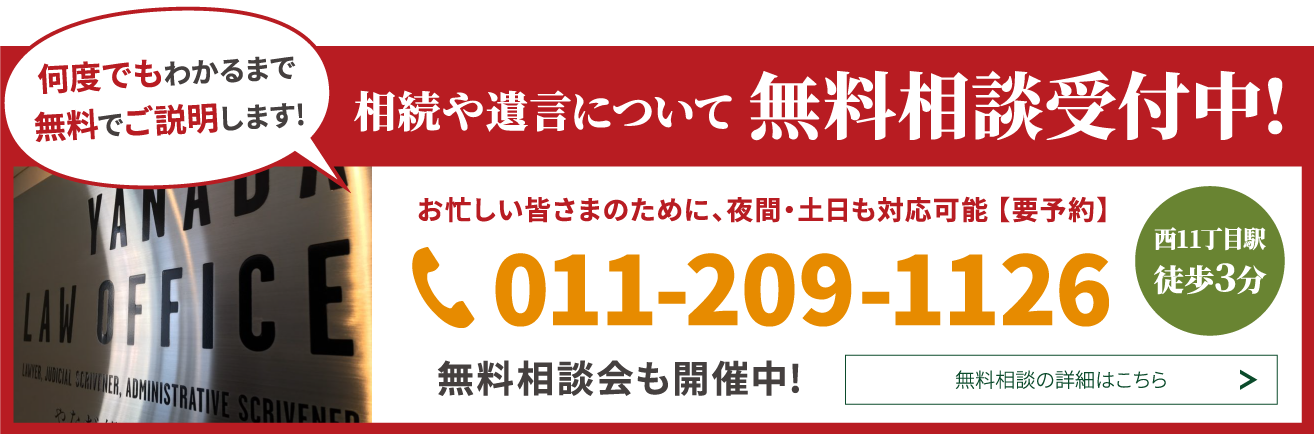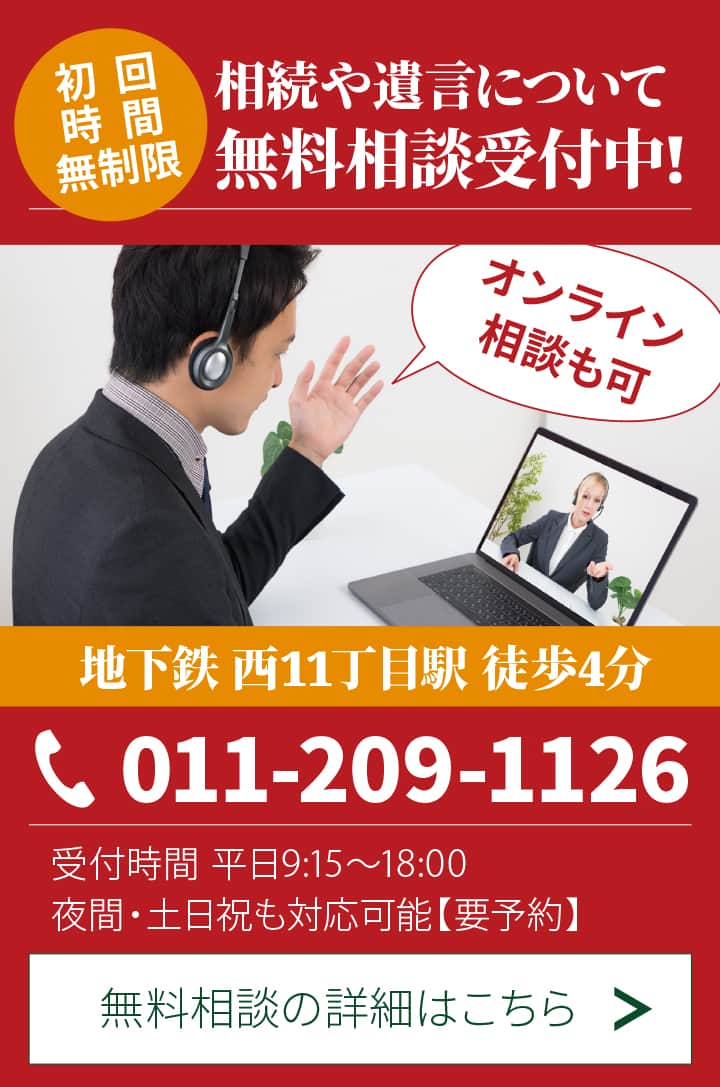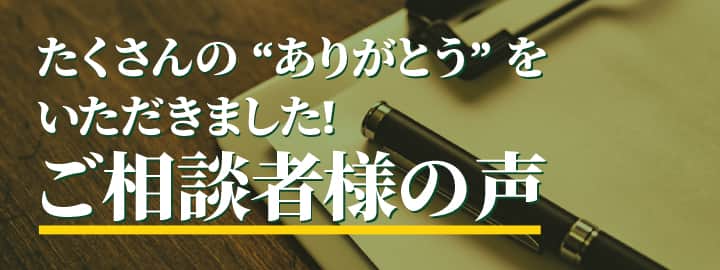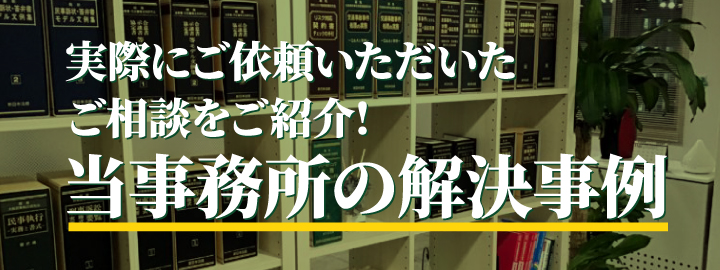前回のコラムでは、最高裁判例を元に、「兄弟姉妹が相続人となる場合における代襲相続人の葉範囲」について解説しました。同判例は、養子縁組と代襲相続が複雑に絡み合う、難解な事例でしたが、今回のコラムでは、養子の子と代襲相続の関係について基本から解説していみたいと思います。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となるはずの者が、被相続人が亡くなる前に死亡していたり、相続権を喪失していたりする場合に、本来相続人となるはずの者の子が代わりに相続する制度です。
例えば、Aさんの遺産は、Aさんの子であるBさんが相続する予定だったのですが、Aさんより先にBさんが亡くなってしまったという場合に、Bさんの子であるCさんが、Bさんに代わってAさんの遺産を相続するというのが代襲相続になります。CさんはAさんから見れば孫にあたりますので、代襲相続を単純化すると「子の代わりに孫が相続する制度」と言えます。
養子も代襲相続人となる
結論から言いますと、養子も実子と同じように代襲相続人となることができます。
例えば、Aさんの遺産は、Aさんの子であるBさんが相続する予定だったのですが、Aさんより先にBさんが亡くなってしまったという場合に、Bさんの子であるCさんが、Bさんに代わってAさんの遺産を相続するというのが代襲相続です。仮にCさんがBさんの養子であったとしても、問題なく代襲相続人として、Aさんの遺産を代襲相続することができるということです。
養子縁組が成立すると、その成立の日から、養子と養親との間に親子関係が発生しますので、養子は養親の子として法定相続人の地位を取得するからです。
養子の子と代襲相続
養子は実子と同じように代襲相続人となることができますが、『養子の子』が代襲相続人となることができるか否かはケースによって異なります。
具体的には、『養子の子』が、養子縁組前に生まれた子である場合には、代襲相続人になることはできませんが、養子縁組後に生まれた子である場合には、代襲相続人となることができます。
以下、両者の違いを具体例を用いて解説します。
養子縁組前の子
BさんにはCさんという子がいました。そのBさんとAさんとの間で養子縁組が成立し、BさんがAさんの子になったとします。つまり、Cさんは養子縁組前に出生しているというケースです。
このようなケースでは、Aさんが亡くなった時点で、既にBさんが他界していたとしても、CさんはAさんの遺産を代襲相続することはできません。
なぜなら、養子縁組が成立すると、養子と養親との間に親子関係が発生しますが、養子縁組前に既に養子の子として出生していた者と養親との間に血族関係が発生するわけではないとされており、代襲相続について定めた民法第887条第2項では、その但書において、直系卑属でない者の代襲相続権を否定しているからです。
上の例で言うと、AさんとBさんの養子縁組によって、AさんとBさんとの間に親子関係を発生させますが、既に出生しているCさんにはその効果は及ばないので、CさんはAさんの直系卑属という地位を取得できません。ですので、直系卑属でない者の代襲相続権を否定した民法第887条第2項但書の適用により、Cさんは代襲相続人にはなれないという結論になります。
民法第887条第2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
養子縁組後の子
AさんとBさんとの間に養子縁組が成立し、Aさんが養親、Bさんが養子となり、その後BさんにCさんという子が生まれたとします。つまりCさんは養子縁組後に出生した子というケースです。
このようなケースでは、CさんはAさんの代襲相続人となることができます。
養子縁組の効果によって、BさんはAさんの子となっていますので、子の子として生まれたCさんはAさんの孫(直系卑属)になるからです。
おわりに
今回のコラムでは、養子の子と代襲相続の関係について基本から解説してみましたが、いかがだったでしょうか。代襲相続自体が一般の方には馴染みの薄い制度であり、難しい印象を受けられた方も少なくないかと思います。そこに養子縁組の話も加わると、一気に複雑さが増してしまいます。代襲相続や養子縁組が複雑に絡む相続のケースでは、権利問題も複雑化することも少なくないので、専門の弁護士に相談することをオススメします。
当事務所は、相続に精通した弁護士が、皆様の相続問題の解決に尽力いたします。初回無料にて相談を行っておりますので、相続・遺産分割・不動産相続など、相続に関することでお悩みのある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。相続人調査や相続財産調査にも対応しております。